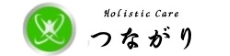相分離とATPの役割

The Legend of ATP: From Origin of Life to Precision Medicine
Metabolites. 2022 May 20;12(5):461. doi: 10.3390/metabo12050461
In the Beginning: Let Hydration Be Coded in Proteins for Manifestation and Modulation by Salts and Adenosine Triphosphate
Int J Mol Sci. 2024 Nov 28;25(23):12817.doi: 10.3390/ijms252312817.
水和と自己組織化

生命には、何らかの秩序を持った構造が自己組織的(自発的)に生まれて、機能を発現しています。
細胞の中というミクロな世界では、タンパク質やDNA、細胞膜などの生体分子が自己組織化し、ある決まった構造を形成することで、それぞれの機能が発揮されています。
この構造が少し変化するだけで、生体分子の機能は大きく変化し、細胞死にいたったり、病気になったりと、生命現象に大きな影響を与えています。
私たちの身体の60〜70%を占め、生命現象に不可欠な物質は、水です。
水は、生体分子の自己組織化に大きく関与しており、「水和」状態が変化することによって、自己組織化構造も変化します。
溶質が水に溶けると、溶質分子と水分子に相互作用が起こります。
溶質と相互作用した水は、普通の水とは性質が大きく異なって、粘性や導電性などの性質が大きく変化します。
またその溶質の周辺での水分子同士の水素結合も変化して、EZ水のような特性を示します。
EZ水については、関連記事をご参照ください ↓
生体中の多くのタンパク質は、ある決まったフォールディング(折り畳み構造)を形成することで、個々の機能を発現しています。
その構造が壊れるとその機能を失ってしまいます。
タンパク質の動的挙動は、周囲の水分子、すなわち水和殻のダイナミクスと複雑に結びついています。
水分子は、極性基や荷電基と水素結合を形成し、疎水性相互作用に関与し、タンパク質の折り畳み、安定性、およびダイナミクスに大きな影響を与えます。
タンパク質の水和殻については、関連記事をご参照ください ↓
タンパク質の安定化と水和水のエントロピーについては、関連記事をご参照ください ↓
相分離とATPの新たな役割

液-液相分離(liquid–liquid phase separation:LLPS)
液–液相分離(LLPS)は、濃度の異なる2種類の水溶液が分離する現象で、これが細胞内でも起こっています。
LLPSによって形成された液滴への親和性の強弱により、液滴内に濃縮する分子が存在する一方で、液滴から排除される分子も存在します。
ある生化学反応に必要なすべての分子が液滴への親和性が高い場合、その反応に関わる分子は液滴内に濃縮されるため、生化学反応は促進されます。
一部の必要分子の液滴への親和性が低い場合、その分子は液滴外へ排除されてしまい、生化学反応は抑制されることになります。
LLPSは、分子濃縮の場としても、分子排除の場としても働くことによって、生化学反応を時間・空間的にも制御しています。
ATPの新たな役割

アデノシン三リン酸(ATP)は、細胞内に 5~10 mMの濃度で存在する分子です。
細胞内に存在する個々のタンパク質の濃度が0.01 mM のオーダーなので、 ATP がかなり高濃度に存在することがわかります。
ATP は生命エネルギーの通貨と呼ばれ、生命活動のエネルギーが、ATP 分子内の共有結合のエネルギーとして貯蔵されると考えられてきました。
エネルギー通貨としてのATPについては、関連記事をご参照ください ↓
近年、ATPの新たな役割として、タンパク質の安定化や凝集の抑制など、別の機能があることが注目されています。
ハイドロトロープ(Hydrotrope)として機能し、高分子の可溶性を維持し、相分離を調節する役割をしています。
相分離によるタンパク質の液滴形成や変性による凝集が、高濃度のATPで抑制されることが明らかとなっています。
アルツハイマーやパーキンソン病など神経変性疾患では、各々に特徴的なタンパク質凝集体の形成が見られると同時に、ATPレベルの低下も認められています。
アルツハイマー病については、関連記事をご参照ください ↓
また、ATP はタンパク質の水和を媒介する能力が高く、タンパク質の構造変化(フォールディング)を誘導することができます。詳しくは、関連記事をご参照ください ↓
まとめ

生命には、何らかの秩序を持った構造が自己組織的(自発的)に生まれて、機能を発現しています。
水は、生体分子の自己組織化に大きく関与しており、「水和」状態が変化することによって、自己組織化構造も変化します。
生体中の多くのタンパク質は、ある決まったフォールディング(折り畳み構造)を形成することで、個々の機能を発現しています。
タンパク質の動的挙動は、周囲の水分子、すなわち水和殻のダイナミクスと複雑に結びついています。
液–液相分離(LLPS)は、濃度の異なる2種類の水溶液が分離する現象で、細胞内でも起こっています。
LLPSは、分子濃縮の場としても、分子排除の場としても働くことによって、生化学反応を時間・空間的にも制御しています。
アデノシン三リン酸(ATP)は、細胞内に 5~10 mMのかなり高濃度で存在する分子です。
近年、ATPの新たな役割として、タンパク質の安定化や凝集の抑制など、別の機能があることが注目されています。
ハイドロトロープ(Hydrotrope)として機能し、高分子の可溶性を維持し、相分離を調節する役割をしています。
相分離によるタンパク質の液滴形成や変性による凝集が、高濃度のATPで抑制されることが明らかとなっています。