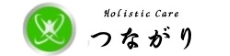嗅覚と鼻呼吸「呼吸位相と認知・記憶」

呼吸位相が外界事象の知覚・認知に及ぼす効果
Japanese Psychological Review 2021, Vol. 64, No. 2, 189–203
呼吸

呼吸は、息を吸うこと(吸気)と息を吐くこと(呼気)が、交互に生じる周期的な活動であり、主に自律神経系によって制御されています。
自律神経については、関連記事をご参照ください ↓
呼吸(内呼吸・外呼吸)については、関連記事をご参照ください ↓
自然な呼吸は、さまざまなリズムと深さで行われ、健常な成人のふだんの呼吸数は、 1 分間に 12~18 回程度です。
呼吸の最も重要な生理学的機能は、酸素を体内に取り入れてエネルギー代謝を行い、それによって産出された二酸化炭素を外界に排出することです。
エネルギー代謝については、関連記事をご参照ください ↓
呼吸をするときには、神経性調節・化学性調節・行動性調節の三者が関わると考えられます。
神経性調節は、橋や延髄にある呼吸中枢と肋間筋や横隔膜、上気道筋といった呼吸筋の間で働く呼吸運動の機構を指します。
呼吸中枢からの遠心性信号が、運動ニューロンを介して呼吸筋を収縮させることで呼吸運動が生じます。
気管支にある肺伸展受容器が、吸気時に伸展すると、その求心性信号が、迷走神経を介して呼吸中枢にフィードバックされ、吸気から呼気への移行が生じます。
化学性調節とは、体内への酸素の取り込みと、外界への二酸化炭素の排出によって、動脈血内の酸素分圧と二酸化炭素分圧を一定に保とうとする機構を指します。
二酸化炭素分圧が上昇すると、脳動脈血中から脳脊髄液に取り込まれる二酸化炭素が増加して、脳脊髄液中で水素イオンが多く放出されます。
脳脊髄液については、関連記事をご参照ください ↓
これによって、中枢化学受容器が刺激され、その興奮が呼吸中枢に伝わり、呼吸が促進されます。
末梢化学受容器は、動脈血中の二酸化炭素分圧の上昇と酸素分圧の低下に反応し、その信号は頸動脈洞神経(舌咽神経)と迷走神経を介して呼吸中枢に伝わります。
このように化学性調節は、呼吸中枢へのフィードバック制御を担っています。
行動性調節は、大脳皮質や中脳といった上位の中枢から呼吸中枢へのフィードフォワード制御を担っています。
行動性調節には、発声や意図的なペース呼吸といった随意的なものと、情動反応のような不随意的なものが含まれます。
意図しなくても自律的に行われている「自然呼吸」は、橋や延髄にある呼吸中枢が制御しています。
また、呼吸のリズムや深さは意図的にも調節可能であり、呼吸のリズムや深さを一定のペースへと随意的に変化させる「制御呼吸」を行うことができます。
「制御呼吸」の場合は、「自然呼吸」と違って、呼吸中枢よりもさらに上位の大脳皮質(運動前野や補足運動野)も関わっています。
人は呼吸を調節することで、発声や咳といった身体活動も行っています。
さらに、ストレスやネガティブな情動反応を抑制するために、意図してゆったりとした呼吸を行うことも実践されています。
呼吸をするとき、多くの人は習慣的に鼻呼吸をしています。
鼻炎や鼻閉塞といった鼻呼吸が難しいときには口呼吸をします。
口呼吸をしたときは、体内に入る気流に適切な温度と湿度が与えられなかったり、菌やウイルスが肺に届いてしまったりします。
口呼吸とアレルギーについては、関連記事をご参照ください ↓
嗅覚と鼻呼吸

ヒトを含めた哺乳類は、周囲の匂いを嗅ぐことによって、食料のありかや危険な敵の存在といった外界情報を取得できます。
たとえ匂いがなかったとしても、鼻から空気が入ることで、嗅覚ニューロンは気流による機械刺激を検出します。
この信号は、嗅球や梨状皮質を通じてさまざまな脳領域へと伝わっています。
自律神経系は大きく交感神経系と副交感神経系に分けられ、互いにバランスをとりながら活動しています。
自律神経系の活動によって、心臓活動や消化、体温など生命に関わる機能が不随意的に調節され、ホメオスタシスが維持されます。
ホメオスタシスについては、関連記事をご参照ください ↓
息を吸い始めると、副交感神経系が一時的に抑制されて、心拍数が増加します。
息を吐き始めると、副交感神経系が一時的に優位になり、心拍数が減少します。
吸気時と呼気時で心拍数が変わるのは、脳幹の呼吸中枢と肺の伸展受容器がそれぞれ脳幹の心臓血管中枢に作用するためと考えられます。
自律神経系は、生命維持機能を担うだけでなく、中枢神経系で行われる外界事象の知覚や認知にも影響を与えています。
心臓活動の位相が、外界事象の知覚や認知に影響を与えることはよく知られています。
収縮期には心室から大動脈や肺動脈に血液が送り出されるために、大動脈弓と頸動脈洞にある動脈圧受容器が活性化し、その信号が脳幹や複数の脳領域(例えば、辺縁系、島皮質)に心周期ごとに伝わります。
しかし、拡張期には動脈圧受容器は活性化しないので、その信号は生じません。
収縮期と拡張期では中枢神経系に伝わる信号が異なるため、心拍位相によって外界事象の知覚や認知が変化すると考えられます。
呼吸も自律神経系によって制御されています。
例えば、自然呼吸のリズムは悲しみや喜びといった感情によって変化することもあります。
逆にゆっくりとしたペースで呼吸をすると、ネガティブな感情を抑制できたりします。
呼吸位相は、記憶(特に符号化や再認)にも影響を及ぼします。
呼吸に同期した神経活動の変化が、前頭前皮質や海馬といった脳領域で生じるのが一因と考えられます。
Zelanoらは、自然に呼吸をしながら、提示される画像を記憶し、その後で再認課題を行う研究を行いました。
吸気時に提示された画像は、呼気時に提示された画像よりもよく符号化され、再認のときも吸気時の方が呼気時よりも成績がよくなりました。
この効果は鼻呼吸をした参加者のみで見られ、口呼吸をした参加者では見られませんでした。
鼻から息を吸ったときに辺縁系(海馬や扁桃体)が活性化することが、再認率の高さに関係している可能性があります。
認知症の初期症状のひとつに、嗅覚の衰えがあることが知られています。
特ににアルツハイマー型認知症では、海馬が萎縮し記憶障害を起こすよりも前に、嗅神経の機能が低下することがわかっています。
認知症の嗅覚の低下は、鼻呼吸の障害と関係がある可能性があります。
アルツハイマー型認知症については、関連記事をご参照ください ↓
まとめ

呼吸をするとき、多くの人は習慣的に鼻呼吸をしています。
口呼吸をしたときは、体内に入る気流に適切な温度と湿度が与えられなかったり、菌やウイルスが肺に届いてしまったりします。
ヒトを含めた哺乳類は、周囲の匂いを嗅ぐことによって、食料のありかや危険な敵の存在といった外界情報を取得できます。
たとえ匂いがなかったとしても、鼻から空気が入ることで、嗅覚ニューロンは気流による機械刺激を検出します。
この信号は、嗅球や梨状皮質を通じてさまざまな脳領域へと伝わっています。
鼻呼吸での呼吸位相は、記憶(特に符号化や再認)にも影響を及ぼします。
認知症での嗅覚の低下は、鼻呼吸の障害と関係がある可能性があります。